【商業登記】取締役の任期の計算について
司法書士の植田麻友です。
株式会社の取締役は、必ず任期が定められています。
任期は、通常定款に「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」と記載されていますが、この〇年の部分が1年~10年の間で定めることが可能となります。
つまり、取締役に就任した以上、10年以上そのままにすることはできず、10年に1度は必ず改選を行い、登記変更を行う必要があるのです。
取締役の任期はいつからスタートするのか
取締役の任期は、「就任した」タイミングではなく、「選任された」タイミングからスタートします。多くの会社は、就任も選任も同じタイミングの場合が多いと思いますが、場合によっては、選任を行う株主総会と就任をするタイミングが異なる場合がありますので、注意が必要です。
なお、この「選任」は選任の効力発生後ではなく、事実行為である選任決議後と解釈されておりますので、任期の起算日を後ろにずらすことはできません。
※株主総会決議を行った日になるので、選任日を●月●日とすることはできない。
ただし、非公開会社(株式に譲渡制限がついている会社)の場合は少し異なります。
非公開会社の場合には下記のような決定が可能です。
・令和6年2月20日開催の臨時株主総会で取締役を選任する。
・「選任の効力は、きたる3月1日から発生する」と決議する。
この場合、3月1日から任期の計算をすることが可能となります。
定款で任期を伸長するにあたり、任期の終期だけを伸長し、それが法定の伸長限度内であれば何も問題ありません。
※「選任後、●●後の日から計算して●年以内に終了する…」と同義。
同様に、非公開会社に限っていえば
「就任後●年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」と定めることも可能となります。
法定の任期伸長限度内であることを考えれば可能となるのです。
選任決議は初日不算入
任期のスタートを選任とする場合ですが、決議の次の日からスタートすることになります。
これは、民法140条の初日不算入に該当します。
民法140条
民法140条:日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
・令和6年3月31日株主総会開催(※任期のスタートは4月1日~)
・令和6年4月1日取締役就任・登記(任期4年・決算3月末)
この場合、期間計算の起算日は「令和6年4月1日」となり、その応答日は「令和10年4月1日」の前日「令和10年3月31日」も4年以内となりますので、任期満了は令和10年の5月開催予定の定時株主総会となります。
任期を個別に定めることは可能か。
取締役の任期は通常、定款で「取締役」全員の任期を統一して定めていますが、取締役ごとに任期を定めることは可能でしょうか。
答えは可能です。
特定の取締役の任期のみを短縮することは可能となりますので、その旨の決議を株主総会で実施することになります。
なお、定款の変更を必ずしも実施する必要はなく、株主総会決議のみで個別の取締役の任期を短縮することができますが、定款もあわせて変更することを基本的にはおすすめいたします。
決議のみだと記録して後から確認しにくいということもありますし、定款の変更がされている方が確実だといえるためです。
まとめ
取締役の任期は必ず満了いたします。
自社でも登記が忘れられていることがないか確認することをおすすめいたします。
関連動画
関連記事


当事務所のご案内
私が記事を書きました。
中小企業をを元気にする活動をしています!!
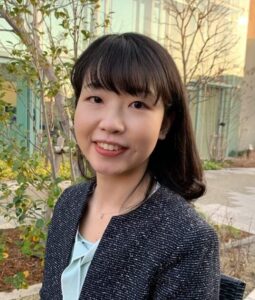
司法書士・行政書士/植田麻友
| 1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。経営者とその家族まで支援できる企業・事業承継支援を行う。 |
オンライン面談のご予約は
下記フォームより承っております。
お気軽にお問い合わせください。






